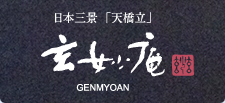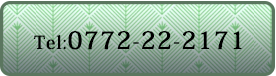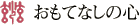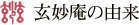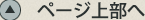日本三景 "天橋立"。遠い昔、イザナギノミコトという男神がイザナミノミコトという女神の住む地に天上から通うために梯を作られたが寝ている間に倒れて出来た。これが名の起こり。その天橋立を玄妙庵から覗くとまるで龍が空に舞うかのように"飛龍観"が眼下に広がる。約80メートルの高台から望むその躍動感溢れる飛龍観を、客室はもとより大浴場からも独り占めできるのはここ玄妙庵ただひとつ。春のいさざ、夏のとり貝、秋の松茸、冬の蟹。料理は旬の食材をふんだんに使った自慢の京風会席料理。
名物・・鯖のへしこ、自家製・・さつまあげ、宮津湾でとれたアサリの赤だしなど朝から御飯が進むこと間違いなし。料理を楽しみながら眺める天橋立、ほっこりとお湯につかりながら眺める天橋立。
是非この絶景を一枚のパノラマ写真でも見るようにお楽しみ下さい。


浦島の湯は開閉式の半露天展望風呂。 天橋立の景色を一望できる浴場で海と空を眺めながら開放感いっぱい。ダイナミックな自然に浸りながらゆっくりリラックスして下さい。


明徳四年五月十八日太政大臣鹿苑院殿義満将軍文珠御参詣の砌り 丹後守護一色満範此に亭舎を設らえて将軍を迎ふ。 将軍登臨して感賞措かず亭に玄妙の二字を賜ふと。 蓋しこの地典雅高潔 脚下に宇内の絶勝天橋立を俯瞰し、遠く水天一碧の汪洋を眸裡に収めて宇宙の玄妙を体得せるより迸発したる語辞なること 田辺旧記に明記する所なり。翌々応永二年九月十九日将軍勝定院殿義勝の文殊御参詣を再び此に迎へ、越えて同九年五月十八日将軍及び 北御所(前将軍義満)の文殊御参詣を夫妻両親と共に三たび迎えて感賞に預かりし亭舎なるも後ち浮屠禅行の修場に充てしことありて玄妙庵と云う。 成相寺古図此所に四阿の亭舎を描き「古堂、座禅所なり」の註記を添え智恩寺古図また亭舎を描くも其れには何んら註記を為さず。俚人堂また亭を呼ばず、庵を通名として「玄妙庵」と称し康正在銘の宝筐印塔、明応在銘の菩薩像など足利盛期の遺物を今に伝えて名残を止どむ。 丙子陽春・永濱宇平誌